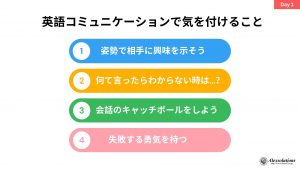【卒業生インタビュー】海外とつながることで、逆に“日本”が見えてきた―社会教育で若者支援を志す大学生が語る「GOAL体験」
目次
はじめに
GOALは、今年でスタートから5年目を迎えました。これまでプログラムに参加してくださった皆さんも、進学や就職などを経て、それぞれの道へと歩みを進めています。
今回は「卒業生インタビュー」と題し、過去の参加者に当時のGOALでの体験や、現在の様子、そしてこれから描く未来についてお話を伺いました。
これからGOALへの参加を検討している方にとって、「こんな人たちが参加しているんだ」と知るきっかけとなり、少しでも参考や刺激になれば幸いです。
大学生AさんのGOAL体験談
2022年当時、高校3年生だったAさんは、まだスタートしたばかりだった第6回目のGOALに参加してくださいました。現在は大学の教育学部に通う大学4年生です。今回は、当時のGOALに参加した時の感想や、現在の大学生活、そしてこれからの進路についてお話を伺いました。
(インタビュアー:池田)

池田:まずは、現在のAさんのことを教えてください。
Aさん:今は大学4年生で、教育学を学んでいて、社会教育というものを勉強しています。
社会教育というものは、人が生きていく中で起こる“生活的課題”、例えば公害とか人権問題とか、いろんな壁にぶつかっていくと思うんですが、それを学びによって乗り越えていこうという学問です。
対象は人が生まれてから死ぬまでの“生涯”で、私は特に若者支援に焦点を当てています。よく、「福祉と教育の違い、境目」と言われているのですが、じゃあ逆にそれが“重なり合う”ところはないのか?と考えていて、若者支援は教育と福祉が両輪となってそれをすべての人に届けられるんじゃないかと思って研究しています。
あと大学では、サークルを頑張っていて、混声合唱団に入っています。人数も100人くらいいて、コンクールも目指しています!そんな感じでサークルも楽しみながら、アルバイトで英会話の先生をしたり、塾の先生をしたりしています。なので、大学生活の指針は、「学業、サークル、アルバイト」の主に3つです。
池田:Aさんが研究している「社会教育」についてもう少し聞かせてください。私たちがよく接する「学校教育」と、何が違うんでしょうか?
Aさん:社会教育は、学校のように「教育を行う」というより、「一人一人の自発的な学びを守る」というところに専門性があります。例えば、安全に話し合いができる場を設けたり、それを専門性をもってファシリエートしたりするという感じです。例えば、公民館や、図書館、博物館、美術館、動物園、自治会などの施設がわかりやすいかなと思います。公民館の館長さんとか。社会教育は一番昔からある学びの方法で、学校教育は近代に生み出されたものです。昔の師弟関係などが社会教育につながっています。
池田:高校3年生の時にどうしてGOALに参加しようと思ったんですか?
Aさん:当時はSDGsに興味があって、世界にいろんな苦しみを持ちながら生きている人たちがいるのに対して、私に何ができるのかなと思っていました。教育にもともと興味があったので、教育っていう大きなテーマから世界の実態を知って、自分にできることを探せないかなと思ってGOALに参加しました。
それまでは、「日本で海外のことを学ぶ」ということはあったけど、GOALでやっているような、シンガポールやスリランカの人たちが現地の実態を教えてくれるというような、「海外から海外のことを学ぶ」機会はなかったので、是非!と思い参加しました。
池田:GOALで一番印象に残っていることは何ですか?
Aさん:英語のプレゼンテーションを作っているときに、シンガポールのサポーターの方が、自分のスライドに英語で指摘をしてくれました。
その時にパソコンの使い方もわからない高校3年生だったので、①英語、②パソコンの使い方、③(プログラム内で)最年少参加だったその緊張や劣等感、この3つの壁を乗り越えるのが大変でした。
でも、サポーターの方が日本語も少し交えながら「ほら、パソコンの右上にボタンがあるでしょう?」とか粘りずよく10~15分くらい一生懸命教えてくれました。申し訳ない気持ちだったんですが、どうにかこうにかして一緒に作り上げた体験は、いろんな壁があったからこそ大きな経験だったかなと思いました。
あと(GOALに参加したのが)高校生活の最後の思い出だったんです。高校生活の中で一番新しい記憶がGOALです。
(*プログラム参加時は2月後半、Aさんはすでに進路が決まっている時期でした。)
池田:その後、GOALに刺激を受けて、海外経験や留学をしたなど変化はありましたか?
Aさん:それがなかなか忙しくて行けなかったんです…。だけど(GOALに参加して)印象が変わったことがありました。参加する前は「海外に行かなきゃ!」とすごく思っていて、海外にばかり目線がいっていました。でもGOALでは海外と日本を比較するために、日本のこともしっかり調べたので、海外だけでなく日本にも目を向けることができました。それでもっと両軸で考えられないかなと思うようになりました。
池田:GOALに参加したことで今の自分に影響を与えたことはありますか?
Aさん:(プログラム中)英語の通じなさがすごく悔しかったので、継続していることとしては英語の勉強です。あの時、英検は十分とっていたはずなんですが、実際に使ってみると全然使えなかった。なので、大学生になっても学びは辞めずにTOEICを受け続けたりして、個人的に英語だけは使っていこうと思っていました。留学経験はないんですけど、悔しかったので勉強しようと思って継続しています。
池田:卒業後にやりたいこと、描いているビジョンはありますか?
Aさん:卒業後は大学院に進んで、そのあと博士までいこうと思っています。社会教育の専門家って意外と少ないんです。ヨーロッパ発祥の「ユースワーク」というのを軸にして研究を続けていて、今後はスコットランドの方に調査に行ったり長期留学も考え中です。日本ではなかなか浸透していない「若者期の保障」といって、若者が試行錯誤しながら大人になっていく、日本でいうと「自立支援」という感じで、就労支援にかた向きがちな若者支援をもっと、若者が自分自身で考えて、若者同士が成長しあえるような学びの場を研究していきたいと思っています。
池田:あまり日本ではないアイデアなんですね?
Aさん:それが、実は日本にもそういうシステムがあるんですよ。 “ユースセンター” という施設です。児童館の若者版をイメージしてもらえればいいかもです。主に北海道や京都にあります。
池田:そういえば近所にもそういうところがありますね。料理したい子がいればキッチンにいって好きに料理ができたり、卓球したり、ガーデニングしたりしてます。
Aさん:そうそう、まさにそれです!
池田:なるほど、イメージできました!じゃあTさんはこれから博士を取ったあとに、そういった施設で働いたりするんですか?
Aさん:今はまだ考え中です。(社会教育に)どうやって関わっていくのか、実践に身を置くのか、専門性を守りながら普及していくのかそのスタイルをちょっと考え中です。
池田:これから関わり方は探していくという感じなんですね。もともと大学に入る前には社会教育について知っていたんですか?
Aさん:それが知らなかったんです!
池田:じゃあ大学に入ったからこそ見つけたん道なんですね。
Aさん:そうです。新たに英語の教員免許も取りました。なので来年からは母校で非常勤講師をしながら大学院に進もうかなと思っています。大学前から持っていた夢と、大学に入ってできた夢と、どちらも頑張りたいなと思っています。
インタビューを終えて
高校時代のSDGsへの興味から始まり、教育の分野で自分に何ができるかを模索し、現在は社会教育という道に辿り着いたAさん。社会教育の可能性や若者支援への思いがまっすぐ伝わってきました。GOALで海外を知ることで、自分の母国である「日本」も知ることができたという言葉も印象的でした。Aさんの今後のご活躍が本当に楽しみです。
今回のインタビューを通じて、Aさんのように海外の人々とつながることで視野が広がり、自分の進みたい道に自信を持てる若者が増えてほしいと、改めて感じました。そして、これからもGOALがそのきっかけの一つとなれたら嬉しく思いました。
2025年7月
アレックスソリューションズ
海外研修事業部 池田